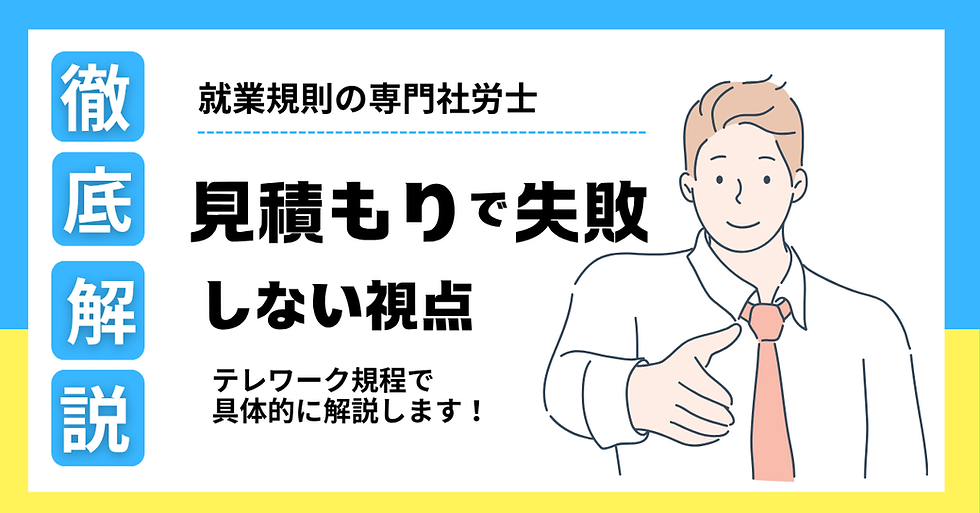【相談事例】就業規則 改定・見直しの料金は安くならないですか?~新規作成との比較
- 特定社会保険労務士 小嶋裕司

- 2024年9月4日
- 読了時間: 6分
更新日:54 分前

ご質問「就業規則の改定・見直しは、全面見直しであっても、一から就業規則を作成するわけではありません。ですから、就業規則の新規の作成より安くならないですか?」
就業規則の見直し・変更のご依頼を受ける際に、非常に多く受けるご質問です。
確かに、就業規則の見直しは、元になる就業規則があります。新規で作成するのと同じ料金であることに疑問を感じる方は多いと思います。
しかし、これだけ多くのご質問を受けるということは、今までに、専門家から明確な回答をいただいたことがないのだと思われます。そこで、この記事では、上記のご質問に対して「ご納得がいくご回答」をさせていただきます。
1.就業規則の一部の見直し・改定
まず、前提として、就業規則の一部を見直す場合には、当然、料金はぐっと安くなります。一部を見直すだけなら、新規作成より費やす時間も短くなるからです「法改正への対応」や「就業規則と会社の実態がずれてきたケース」などが典型です。
しかし、その場合、変更箇所の量と質によって料金が変わります。一律の料金を頂いている事務所はないはずです。当事務所でもお問合せを頂ければ、概算お見積りをご提示するという形にさせて頂いています。以下のページから「お申込・お問合せ」をいただいています。お見積もり専用ページ
あくまでも、この記事で詳しく解説する内容は、「就業規則全体を見直す場合」や「会社が何らかの課題を抱えて就業規則を大きく見直す場合」の話です
2.就業規則の全面見直し・改定の料金
結論から申しあげると、就業規則の「全面見直し」は、新規作成より安くなるケースは少ないです。ケースによっては、新規作成より高額になる場合も出てきます。理由は、「就業規則の見直し」は「就業規則の新規作成」より大変な業務(又は手間のかかる業務)になるケースがあるからです。
当事務所は就業規則の新規作成のご依頼は少なく、ほとんどが「現在ある就業規則を見直したい」というご依頼です。したがって、就業規則の見直し専門の社労士事務所といって良いと思います。今まで、あらゆる就業規則の見直し業務を行ってきました。
就業規則の見直しの専門家の立場から書かせて頂いていますので、この記事をお読みいただければ、就業規則の見直し業務が非常に高度な業務(又は手間のかかる業務)になることをご理解いただけると思います。
就業規則の変更・改定を専門家に依頼することをご検討している全ての方のお役に立つ内容になっていると確信しております。ぜひ、最後までお読みいただければと思います。
■ 就業規則の「全面」見直しが新規作成より大変な理由
主に、2つの理由があります。
一つ目は、お客様企業1社1社異なる就業規則に合わせた見直しが必要だからという理由です。
二つ目は、ケースによっては、就業規則の不利益変更の問題が生じる可能性があるからという理由になります。
これだけではわかりずらいと思いますので、以下で詳しく解説いたします。
理由1:お客様企業の1社1社異なる就業規則に合わせた見直しが必要
就業規則を作成するに際して、多くの専門家は、事務所のひな型を使用しています。雛型を使用せず、毎回、1から作成していたら、莫大な時間がかかります。その分、料金もかかります。6~8割は全ての企業に共通する内容です。時間を減らし料金を抑えるためにも専門家はひな型を使用しています。
しかし、就業規則の見直しの場合には、お客様企業に、既に就業規則があり、その規程を変えていくことになります。当然、専門家が普段使用している雛形を使うより変更にお時間がかかります。
パターンA 専門家の提供するひな型(毎回同じ)を企業の事情を伺って変更していく |
パターンB お客様企業の就業規則(毎回違う)を企業の状況・要望に合わせて変更していく |
パターンAよりパターンBの方がお時間もかかり手間のかかる内容になるということはご理解いただけると思います。内容を追加する場所も会社ごとに変わりますし、就業規則の条文を変更・修正する場合も、完全に条文ごと「取り換える」ことはできず、今ある条文に内容を追加・修正・削除していくことになります。
変更する際には、今ある条文の何が問題かをお客様企業にご説明しつつ変更していくことは大変な作業です。さらに、矛盾点や不明な点(なぜ、このような条文があるのか等)が存在していた場合、既存の条文を慎重に確認し、不明点や矛盾を解消していく作業も必要になります。
理由2:就業規則の不利益変更の問題が生じる可能性
また、就業規則の見直しの場合には、就業規則の不利益変更という問題もでてきます。慎重に進める必要が出てきます。不利益変更の話は別記事で詳細に書いております。以下の記事をお読み下さい。
3.就業規則の改定・見直しの料金 まとめ
今まで、就業規則の「全面改定・見直し」は大変な業務になるので、安くはならない理由を書かせていただきました。だからと言って、当事務所は新規作成より高額な料金は頂いておりません。また、当然、当事務所の雛形を押し付けるようなこともいたしません。
御社の就業規則の原型及び条文(細部)を大切にしながら修正を加えていきます。つまり、今ある就業規則の良さを活かしながら変更していきます。
そもそも、原型の就業規則から「全くの別物」に変わったら、社員の皆さんもビックリするじゃないですか。自分の事務所で普段使用している雛形を使用した方が専門家にとって楽ではありますが、それは、専門家の都合に過ぎないのではないでしょうか。
今回の話は、もちろん、一般化できるものではありません。お見積額をお知りになりたい方は、以下からお申込・お問合せください。冒頭でお伝えした通り、就業規則の一部を改訂する場合のお見積りにもご対応しています。概算でよろしければ、具体的な金額についてお答えできます。
なお、就業規則の改定のお見積りの前に、就業規則の大まかな料金をお知りになりたい方は以下をご覧ください。当事務所の料金の考え方を解説しつつ、よく頂く典型的な3つの業務例もご紹介しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
執筆者
フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
代表・特定社会保険労務士・事業承継士
小嶋裕司
執筆者プロフィール
当事務所のクライアント企業は、就業規則は既にあるけれど、新たに生じた人事労務の課題に対して、「自社の就業規則では対応ができない」とお困りになり、お越しになるケースがほとんど(お客様の9割弱)である。就業規則の見直し・改定中心の専門家と言える。また、長い歴史を持つ企業から選ばれており、お客様の6割が創業30年(3割が50年)以上の老舗企業である。更に、二代目社長が経営する会社が全体の5割以上を占めており、就業規則専門の社会保険労務士事務所として、これらのデータは非常に特徴的なお客様構成だと言える。