二代目社��長の課題解決社労士/変革期を迎えた老舗企業の人事労務問題に強い
就業規則 作成・見直し専門 ‐ 人事・労務問題の割合 99% 超
東京都大田区|全国対応 フェスティナレンテ社会保険労務士事務所
�就業規則の整備は会社に変化が生じます。仮に、社内で反発が起きたとしても、新制度の導入までご支援します
当然、これらについて新たな制度を導入しようとしたり、既存の制度を変更しようとすると、会社に変化が生じます。
そうなると、一部の企業では、変更の際に、社内での調整が必要になります。まず、役員の皆様同士で意見の対立が生じることがあります。何を重視するかで、とるべき方策が変わってくるからです。また、労働条件の変更などについては、社員の反発が起きることもあります。法的にも丁寧な説明や(変更後の内容によっては)同意が必要になることもあります。こういった事情から、制度の変更について進まず、ペンディングになっている悩みを抱えた企業は多いです。
しかし、このような調整が必要になるのは、会社の成立・役員の皆様の就任の経緯及び役員構成、立場の異なる利害関係者の存在、社員の皆さんの業務内容及びそれに基づく会社との関係性、並びに「変更の内容」等によるもので、条件を満たした企業では必然的に生じるものです。これらは、リーダーシップ等の問題ではなく、組織の構造上の問題や法的要件に基づくものですので、経営者の責任ではありません。
しかし、必然的に生じる問題だと言っても、就業規則に関する問題は、労働者を守る労働法があります。そのうえ、労働条件は人件費が絡む問題です。会社としても人件費の総額は決まっています。それだけで、経営者の頭を悩ます問題です。そのうえ、社内の調整まで必要となってくると、現実的な解決は非常に難しい問題になります。
しかし、仮に、就業規則の変更を進めていく中で、この様な問題が生じたとしても問題ありません。スムーズに新制度(就業規則)を社内に導入するところまで当事務所ではサポートを行っております。
このサービスの一環ととして、当事務所では、ご希望に応じて、役員会議での意見の集約・ご説明から、就業規則の社員への説明(説明会)のサポートまで提供しております。会社の個別の事情をお聴きし、毎回、クライアント企業と話し合いながら慎重に行っています。
開業当初から、当事務所では、このような相談を受けてきましたが、2011年からファシリテーションを学んだ※ことをきっかけに、スムーズに新制度へ移行するサービスを提供売ることができるようになり、今に至ります。
※ファシリテーション活動の歩み
社内ビジョン浸透の3000人対話集会を行った代表(中島 崇学氏『一流ファシリテーターの空気を変えるすごいひと言』著)の元、クローズドな場で(厳しい選考を経て)、3年弱121日に及ぶ活動で本格的にファシリテーションを学んだことがきっかけとなりました。
事務所代表のファシリテーション活動の詳細については以下のページをご覧ください。このスキルが、新制度の円滑な導入と経営者の皆様との信頼関係構築に大きく貢献しています。
以下で当事務所の「新制度へのスムーズな導入事例」を挙げさせていただいています。守秘義務等がありますので、抽象的な内容になっておりますが、その点はご了承ください。
新制度をスムーズに導入した事例紹介
事例1 親子間での会社の方向性をめぐる意見の相違
先代の社長と2代目社長との対立。会社の賃金制度を変更しようとした二代目社長と反対の先代の社長。新制度への不安から先代の社長が反対していましたが、私がファシリテーターとなって、双方のご意見を伺ったところ、肝心の部分では対立していないことがわかりました。二代目社長の方針をほぼ受け入れつつ、先代の社長の心配も解消する形で新制度へ移行できました。
事例2 ご家族間(役員間)でのご意見の相違
あるファミリービジネスの会社で、厳しめの就業規則にしようとしたところ、「就業規則でガチガチに縛ったら社員が付いてこない」「いや、甘くしすぎると会社が乱れてしまう」とご家族間(役員間)対立しておりました。しかし、どちらのご意見も正しく、肝心の部分では対立していないことがわかりました。そこで、そのような制度設計をすることで、新制度へスムーズに移行いたしました。
事例3 合併会社での役員の方針の相違
ある合併企業では残業代の問題で行き詰まっていました。直観タイプの社長と実務家の役員間で具体的な制度設計でまとまっていなかったようです。そこで、私がファシリテーターとして、�役員会議にご参加させていただきました。その結果、社長の「言葉にならないご意見」を言語化することができました。方針は一致したため、あっさりと解決しました。
事例4 グループ会社での役員間の方針の対立
ある子会社には、親会社から出向してきている役員の方がいて、新制度の導入には、取締役会でその方の了承をえつつ、親会社との調整(承認)も必要でした。当事務所では、1つの問題に対して、複数の解決策をご提案できることが多く、出向役員の方の懸念事項も踏まえつつ親会社の承認も得て、新制度に移行いたしました。なお、同じような事例で、上場企業のグループ会社の経験もあります。
事例5 社員の意見を反映する慣行の会社
ある会社では、社員の親睦会があって、新しいことを始める際には、親睦会の反対がないことを確認する慣行がありました。しかし、今回は、新制度に移行するのに会社の方針は変えられません。そこで、社員の意見も組むようにしつつ、会社の方針を変えずに新制度へ移行するところまでサポートして欲しいということでした。書面で上がってきた様々なご意見を就業規則に反映することになりましたが、会社の方針は変えることなく、社員の皆さんのご意見も概ね反映できました。一部、反対がありましたが、個別の対応といたしました。
事例6 経営上必要だが、社員に受け入れられにくい制度の導入
ある会社では労働条件の変更を含む社員に受け入れられにくい制度の導入が必要となりました。新制度には強い合理性があり、会社の状況を考えれば、ほとんどの社員は理解してくれる内容です。ところが、社長は過去の経験から一部社員の強い反発を懸念していました。そこで、社員の方が過去に反発した内容を伺うことにしました�。それを踏まえて、適切な時期に、適切な内容を社員の皆様にお伝え(ご説明)することで、今回に関しては新制度への移行に大きな反発が起きず移行できました。
専門家に相談することにご不安な方へ
~組織の問題を相談したら会社が混乱する!?
これらはごく一部の事例ですが、様々な事例を取り上げました。もちろん、利害関係者が完全にご納得いったケースばかりではありません。就業規則を一から作り直したこともあります。また、いくつかの案を作成し同時進行で進めたこともあります。採用になった案以外はボツになってしまいましたが、当初から想定されることですので料金を追加でいただくことはありません。仮に、理想的な解決策に至らなかったとしても、クライアント企業に「もう十分です」と仰っていただけるところまで伴奏させていただいてきました。
また、「こんなことを労働法の専門家に相談したら面倒なことになる」という心配を持たれる方も多いと思います。「コンサルタントが入ると会社が混乱する」という心配をお持ちの方も多いようです。しかし、その心配には及びません。当事務所のサービスは「ファシリテーションの技術※」を活用した課題解決ですので、私の意見や価値観を押し付けたりすることはないからです。
※ファシリテーションの技術の本質は?
ファシリテーションの技術の『本質』は、場(組織)の言葉にならない『思い』を言語化(目に見える形に)し、異なる意見の方々が合意できる内容にまとめる技術です。
もちろん、意見を求められれば見解をお話させていただきますが、原則として、プロジェクト全体の進行を円滑に進める存在として活動させていただきます。クライアント企業の価値観を大切にするというのは当事務所が最も大切にしていることです。
また、就業規則の整備が終わった後も、当事務所はサポートをします。新たな就業規則が社内でスムーズに適用されるためには、就業規則の社員への説明が必要だからです。社員からの質問に適切に答えるためのサポートとして、また、説明会の進行役として、引き続きお手伝いします。新たな制度がスムーズに導入されるまでのサポートを提供します。御社が新制度を社内の反発を受けることなくスムーズに導入したいと考えているなら、強いお力になれます。
ただ、確実に、お役に立つとは言えません。そこで、当事務所では、1日、お時間は無制限で就業規則無料コンサルティングを行っています。その場で、私がどのような業務を行うかご確認ください。就業規則に関することであれば、どのようなことでも承っていますので、こちらからのページ(無料コンサルティング)からお申込ください。
しかし、中々、専門家に込み入ったことをご相談することへのご不安は解消できないかもしれません。それでも、ご不安な方は以下のページをお読み下さい。当事務所の考え方や方針を書かせて頂いてます。
プロフィール・経歴
当社労士事務所は就業規則の専門事務所です。就業規則の関連業務は事務所の業務の99%を占めています。当事務所が就業規則の作成・見直し業務を請け負った際、大半のクライアント企業から社内調整に関するご相談をいただいています。役員会議での意見集約、親子間・役員間での方針の対立解消、社員への説明方法、社員の意見反映など、就業規則の内容作成だけでなく、社内にスムーズに導入するまで支援することが当事務所の大きな特徴です。
当事務所は、様々な会社に就業規則作成・適用支援サービスを提供してきました。ファミリービジネス(家族会議)での意見とりまとめは当然のこと、株主への説明責任が求められる上場企業や、様々な立場の役員がいる上場企業のグループ会社等への本サービスの業務経験もありますが、特に、二代目社長の会社での経験が豊富です。
これらのサービス提供において、当事務所はファシリテーション技術を活用しています。ファシリテーションの技術とは、『場(組織)』の言葉にならない『思い』を言語化(目に見える形に)し、異なる意見の方々が納得できる内容にまとめる技術です。
そのおかげもあり、「小嶋さんは人の価値観を否定しないから、何でも話しやすい」とクライアントから評価を受けており、そのため単純な書類作成だけでなく、より深い組織の課題解決を任されることが多くなっています。
このような実績と評価を得られるようになったのは、前述の通り、2011年に始まったファシリテーション活動が大きく貢献しています。社内ビジョン浸透の3000人対話集会を行った代表(中島 崇学氏『一流ファシリテーターの空気を変えるすごいひと言』著)のもとで、3年弱、121日、ファシリテーションを学びました。さらに、2017年、その経験を「青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー育成プログラム」で学術的・理論的に学び、体系化したことで、より効果的なアプローチが可能になりました。
これらの経験と学びが、当事務所の課題解決アプローチの基盤となっています。
本サービスの具体的な手法を紹介した電子書籍
2020年に、Amazonランキング9部門1位を獲得
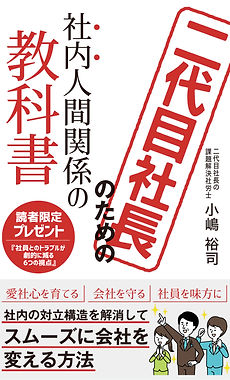
Amazonランキング
9部門1位
社内制度(就業規則)を社内の反発なくスムーズに変更する手法を書いた電子書籍が2020年8月に行ったキャンペーンでAmazonランキング9部門1位になりました。二代目社長を対象にした書籍ではありますが、ファシリテーションの手法を使った内容ですので汎用性があります。しかし、本書籍は2022年12月末をもって出版を停止しました。その理由としましては、進化し続けている、弊所のコンサルティングを直接受けることで、より具体的かつ効果的な支援を受けていただきたいという思いからです。ぜひ、就業規則無料コンサルティングを受けていただきたいのです。
費用・料金
以前、知り合いの士業の方から、「親子間で社員への対応を巡って意見の対立があるので、経営者を紹介したい」というご相談を受けました。その際、「高いんでしょう?」と恐る恐る聞かれたことがあります。そんな疑問や不安を払拭するべく、当事務所の料金体系について明確に説明します。
当事務所の標準的な料金には、就業規則に関連したご相談や資料作成は含まれます。当然、社内コンセンサスに関する業務も含まれます。つまり、本サービスは、原則的な料金に含まれています。更に、就業規則の変更や作り直しにかかる費用も原則的な料金に含まれています。例えば、役員会議での決定により、就業規則を一部変更することになったとしても、追加の料金は発生しません。役員会議に出席することも同様です。それは、就業規則(ルール・労働条件)を完成させる上での必須のプロセスだからです。
しかし、当事務所の拘束時間が増加するケース、例えば、それにより、打合せの回数が大幅に増えた場合、あるいは就業規則の社員説明会を行う場合など特別の業務は別料金となります。また、不測の事態に対応するために、スケジュールに余裕を持つ(逆に、超特急で行う)こともできますが、その場合も料金に反映されます。
これらの詳細はお問い合わせいただければ、具体的にご説明いたします。お客様のご要望に合ったサービスを提供するため、料金については個別に対応させていただきます。ご要望をお伝えください。
具体的な料金に関しては、料金ページの以下の部分をご覧ください。


